飲食業の労働時間の長さは異常です。しかもそれがあまりにも当然になっています。そのため正当な主張ができない、声を上げることもできないという怖さがあります。
12時間くらいならまだいい方で14時間以上が常態化しているところも珍しくありません。私自身飲食業界に15年以上いましたが、この記事では労働時間について実態を再確認するとともに、長くなる理由についてまとめていきます。
統計と実態
まずは飲食業界の労働時間の状態についてです。
厚労省の【PDF】第4章 外食産業における労働時間と働き方に関する 調査から見てみましょう。この調査を細かくみていくとたいへんなので概要だけ一部抜粋します。
平均的な月における正規雇用者1人当たりの月間時間外労働時間は、「10 時間以下」が 33.3%で最も多く、次いで「10 時間超 20 時間以下」が 20.5%、「20 時間超 30 時間以下」が 10.7%であった。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000174214.pdf
これを見るとなんだ少ないじゃないか、と思うでしょう。ただこの調査は回収率が11.3%ととても低く、全く実態を反映しているとは言えません。
では実態はどうなのでしょうか。外食店長「定額働かせホーダイ」の過酷な実態という記事からの引用です。
私が勤めるツナグ働き方研究所が今年7月に飲食業店長経験者(現職、過去経験含む)200人を対象に実施した「飲食店店長実態調査」によれば、月間240時間以上働いている飲食店店長は、通常時でも43%、繁忙期には67%に及びました。これは週休2日、残業がいっさいない人と比べて、「過労死ライン」とも言われる月80時間近い残業を強いられているのと同様です。
https://toyokeizai.net/articles/-/190608
こちらは調査方法を含めて実態を反映していると思います。繁忙期は3分の2以上がおよそ過労死ライン越えです。また例えば2016年には月200時間を超える残業を超えるサービス残業などでうつ病になり提訴ということがありました。
私自身もレストラン店長の一か月以上連続出勤など見てきました。月の労働時間が300時間が普通(12~13h×25日)で、400時間以上もちらほらいる(休みなしか月1休み)職場もありました。
労働時間が長くなる理由3つ
人手不足
まずはこれです。残念ながら業績が悪くない店舗や企業でも単純にバイトなど人手が足りず正社員が長時間労働でカバーするという実態があります。
帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2019年10月)」からみてみましょう。従業員が「不足」している上位10業種(非正社員)をみると「飲食店」は78.3%(1位)となっていて、8割近い企業で人手不足を感じている状態です。これは全体の29.3%に対してダントツで、2位以下にも大きく水をあけています。
その理由としては以下のようなことがあり、これらが連鎖して悪循環になっています。
- 人の入れ替わりが激しくなかなか定着しない
- 常に新人を抱えていて教育の負担も追いつかない
- 募集をかけても昔のようにすぐに応募がない
- 従業員一人当たりの負担が多くなる
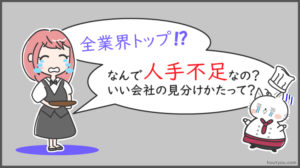
無理な目標と残業前提の計画
本社から店舗に課される利益目標に無理があるというパターンです。売上目標自体にも無理があるケースも多いですが、大抵は主に人件費コストが問題になります。事実上の上限以上にバイトを使うことができないので、結果として社員のサービス残業に頼ることになります。当然店長自らも長時間労働せざるを得ません。
そもそも社員のサービス労働を前提に経営計画がなされているというのも業界全体の悪習です。経営者側からみると、みなし残業※は使い切るのが当たり前です(むしろみなし残業すら満たさないのは給料泥棒くらいにはっきり宣言されたこともあります)。実際そうしないと利益が残らない、役員や株主の取り分がなくなるというところが多いです。
また解消しようにも、今まで社員の長時間労働で成り立ってきた外食産業・飲食店の相場というものがあります。ある企業が社員の残業をゼロにするという目的で値上げしても当然顧客がついてきません。よほどシステムを整えるかウリがある企業でしか実現できません。

営業時間が長い
店舗の営業時間が長いことから自然と労働時間が長くなります。バイトに任せて回る仕組みを作ればいいと思いそうですが、そう簡単にはいきません。以下のような理由があります。
- 技術的に社員でないとできないことがある
- バイトの埋め合わせ(急な休み、急な退職)
- 人手不足
- 仕組みを作ったら回っていない他店に優秀な社員を持っていかれる
また責任者だと結局営業時間中はいつトラブルが起きて呼び出されるかもわからないので気が休まりません。
今は減ったかもしれませんが、私が20歳くらいの頃(15年くらい前)は社員は営業時間中は朝から晩までいるというケースが多かったです。夕方2~3時間の休憩を挟んで14~15時間拘束などです。今ならシフト制にしないとだれもいつかないような体制ですので徐々に減ってはきた気がします。
ですが飲食店ではこういう体制が昔は当たり前だったので、やはり営業時間の方に労働時間を合わせるという考え方が根強く残っていると感じます。

短くする方法
実行して効果を出すのが非常に難しいのを承知であえて方法を挙げておきます。
管理者・社員として短くする方法
王道の方法です。
- 店舗オペレーションを見直し、無駄の削減・効率アップを行なう
- 新人社員やアルバイトの教育、定着する環境づくりを行なう
ですがもちろんこう書いて実行できるほど簡単ではありません。企業自体がブラックな場合は努力してもどんどん搾取されるだけになる可能性がありますし、そこまでの時間や労力は大変なものになります。
自分自身を優先して短くする方法
個人として労働時間の短縮を目指す方法もなくはありません。
1つは店舗スタッフよりも上を目指していくという方法です。ですがエリアマネージャーや経営幹部になったほうがよけいに長時間労働になる、またはストレスを抱えてより苦しくなるということも多いです。
私がいたある会社でも店長はほとんど休みなし、マネージャーになるとさらにその上をいき車で寝泊まりしていました。
もう1つは権利を主張して自分の労働時間を守るという方法です。例え怒られようがどんな顔をされようが出社時間から数えて定時になったら帰ります。正当な主張ですが相当な軋轢があるでしょうし、いつ辞めてもいいという覚悟でないと実際にはできません。
転職する
このようにブラック企業や店舗自体に問題にある場合は個人の努力ではどうにもできません。
結局ホワイトな環境に転職するのが一番現実的です。今は働き改革などもあって本気で取り組んでいる企業も多いです。売り手市場なので思っているよりあっさり転職が決まったという人も多いです。
飲食業界に特化した転職支援サービスはおすすめです。飲食経験者が担当してくれるので条件のすり合わせがスムーズですし、企業のリアルタイムな情報を教えてくれます。
フーズラボは飲食業界専門の転職支援サービスです。飲食業界に精通しているキャリアアドバイザーがいるため、業界特化ならではのリアルな情報を提供してくれます。そして将来のキャリアまでしっかり考えたマッチング、丁寧なサポートがあります。
| 特徴 | 飲食業界の転職支援で圧倒的に成長しシェアが高い。非公開求人、優良企業求人。 |
| 実績 | 年間3,000名以上の転職支援。転職エージェントランキング3冠獲得(※)。 |
| 対象地域 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、名古屋、福岡 |
現在、飲食業界の求人は多いものの、実際には選ぶのが難しいと感じている人は多いようです。そのため飲食専門の転職エージェントであるフーズラボの強みが生きてきます。企業や店舗の実情をしっかり把握している担当者が希望に沿ったマッチングと推薦等サポートを行ってくれます。
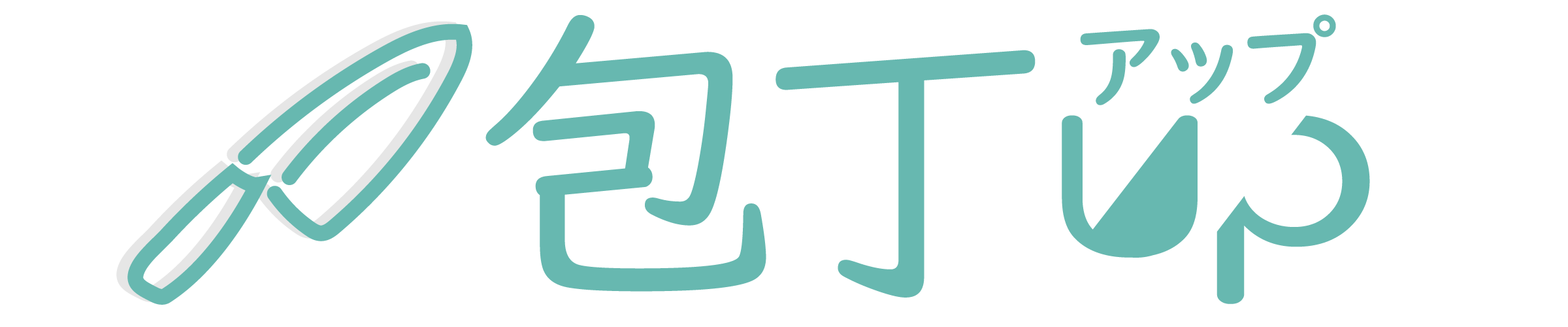
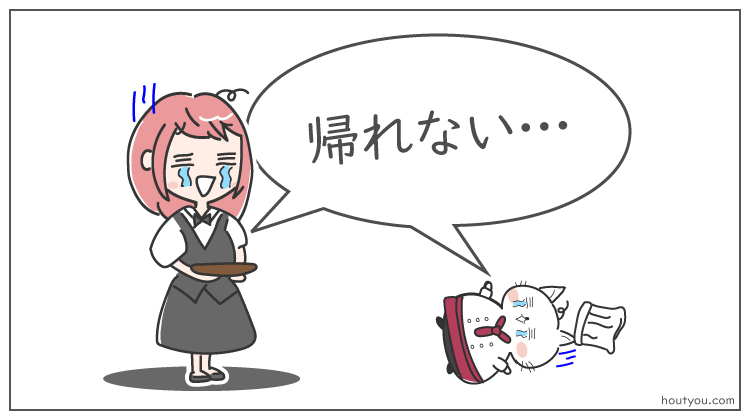

コメント