ひとりボウリングをしています。アベレージというのは徐々に上がっていくものだと思っていました。途中上がったり下がったりはあるにしても一定のペースで上昇していくというイメージです。
でも実際はそういう風にはなりませんでした。一回の気づきや修正によってアベレージがグッと上がったので、そのことについて書きたいと思います。
※あくまでアベレージ170程度までの話です。それ以上になったらたぶん反復練習や微調整を繰り返して徐々にあげていくしかない気がします。
ボウリングのアベレージは繰り返し練習で上がるという勘違い
一人ボウリングを始めたときアベレージは140台でした。なので年単位でアベ160→170→180という向上をイメージしていました。
それは「定期的に繰り返し練習して体に覚えさせていくゲーム」という認識だったからですし、アベ170はけっこう高い壁と思っていたからです。でもアベ170(30ゲーム平均)は1か月ちょっとでクリアしてしまい意外でした。
正直「練習で身体に覚え込ませた」みたいな要素はありません。ある瞬間から突然階段をポーンと上がってしまった感じです。なので練習というより、ある瞬間の「気づき」です。投げている最中に「あ、この感覚すごくいい、この投げ方ならミスる気がしない。」とか「今のスピードと回転だとピンアクションが全然違ったぞ。」といったことです。
もちろんその一回を再現するためにそのあと5~10ゲームとかかかります。その中でいろいろ試してはっきりさせていくので厳密に言うと「瞬間」ではないですが。ただその最初の瞬間に気づきを得られなければ、自分の中でなにも動かず始まらずにその後の5~10ゲームも過ぎていったと思います。これだとまさに「ただの繰り返し練習(練習している感)」になっていたことは確かです。
劇的に向上したタイミング
個人個人で現状も癖も違うはずなので一人の具体的な事例を書くことにあまり意味は感じません。ただ一応どういう風にアベレージが上がったかを書いてみます。※他にも大小いろいろありますが、一番わかりやすい例です。
立ち位置をど真ん中に変更
ハウスボールのストレートですが最初は右端から投げていました。角度をつけたほうがストライク率が高くなり、スプリット率も下がると思っていたからです。
でもある時に立ち位置をど真ん中に変更してみました。ポケットも狙わずヘッドピンのど真ん中狙いにしました。これだけでヘッドピンに当たる確率が急上昇しました。ヘッドピンに当たったときのストライク率やスプリット率も斜めからと比較して別に変わりませんでした。
ど真ん中に変更したのは、やはり斜めに安定して投げるのは人間にとって難しいと感じたからですし、ヘッドピンに当てることの重要性にも気づいたからです。
なお真ん中にしてよかったことは結果以外にもたくさんあります。フォームのズレや修正が楽になったことです。具体的には、まっすぐ歩けているかは一目瞭然になりました。リリースした直後の左足の位置や方向も1cmレベルで確認可能になりました。またボールがレーンについた瞬間から、狙いとどのくらいずれたかもすぐに把握できるようになりました。
私の場合そのまま真ん中から投げるのを固定化しましたが、上記のように練習(確認)過程としてもよいと感じます。
ボールを引く位置の意識
ボウリングは振り子で投げるのでどこにボールを引くか(持ち上げる方向)は重要です。でも理屈はわかっていたつもりでしたが、その重要性がわかっていませんでした。
あるときこの意識が弱いことに気づき、助走中の意識をぜんぶ体の後ろにしたところ急激にコントロールが上がりました。
具体的には、狙うスパットと右腕が一番下にきたときのボール位置を直線で結び、その延長線を体の後ろに引きます。その線に沿ってボールを持ち上げ、その線を通って前に帰ってくるという感じです。
それまでは意識はほとんど前でした。つまりスパットや床板を見つめてそこに投げようとしていました。でも実際には助走中、特にボールを持ち上げたときと返り始めたときにほとんど勝負が決まっていると感じ、意識をほとんど体の後ろに持っていきました。
その結果はじめて自分のボールの行き先を信じられるようになりました。つまり「線に沿えた」と感じたときはボールを離した瞬間から成功を確信できるようになりました。それまではボールがレーンの途中まで進まない限り上手くいったのかどうか把握できない状態でした。
また意識を体の後ろに持ってくることでボールを持ち上げる高さも安定させられました。その結果球速も上がり、かつ安定するようになりました。球速は最初26~27キロ台くらいだったのが今は30~31キロ台くらいになりました。ストライク率も上昇しました。
練習だけでなく実験が大事
今回ボウリングに取り組むに当たって最初から重視していたキーワードは「練習」ではなく「実験」です。とりあえず結果に影響しそうな要素を洗い出して気になったことはやってみるという感じです。
試せることはたくさんありました。球速、縦回転、立ち位置、視点、ボールを持ち上げる高さ、助走などなど。※球筋はストレートと決めているのでフックはなし。
スコアは捨てると決めたゲームでは、助走なしなどいろいろやってガターを出したりもしました。※助走なしは発見が多いのでおすすめ。
また普通にスコアを出す練習でも10フレの最後の一投なんかはほとんど「実験」に使ったりしました。最大球速を試したり、ボールを限界まで高く振り上げたり、重いボールにしたりなどです。
これらをやっていたのがはやめの発見や気づきにつながりました。
付け加えるとボウリングは各指標がわかりやすいので、アベレージよりもそちらを見るのが課題洗い出しの上で大事だと思います。指標とはオープン率やノーヘッド率などです。今はスコアを記録・分析できるアプリなどが豊富にあるのですぐに把握できます。
成功法則を探し出そうという意識は大事なのかもしれない
自分の失投の原因や自分なりの成功法則に早めに気づけたのは運もあったと思います。だれかに見てもらったり撮影したわけではなく、投げているときに感覚的に「あ!」とひらめいたり気づいたりしただけなので。こういうのって本当にたまたまみたいな部分もあります。もしそれが半年後や一年後とかになったらその間はずっと横ばいになってしまったかもしれません。
ただ今回のボウリング開始時は、常に感覚と結果を照らし合わせるクセは持っていました。ちょうどボウリングの前にバッティングセンターにハマったときにかなり自分なりに検証を重ねていたからです。バッティングも自分の中での大きな気付きをしたときが何度かあり、その時に一気に伸びました。ちなみにバッティングに関しては発見が遅く、後から考えたら「それ当たりまえだろう」みたいな気づきに半年や一年かかりました。今考えると「実験」という視点はほぼなかったので、成長が遅くて当たり前だったと感じます。
せっかくこの経験があったのに、ボウリングに関しては当初「ただ繰り返し練習あるのみ」と考えてしまっていたのは我ながら残念です。でも潜在的には常に成功法則を探し出そうとするクセはついていたと思われます。
なおぜんぶ自己流なので間違った意識や法則はあると思います。なので今後も現状の成功法則とは正反対のやり方なども試そうと思っています。
アベ170までの世界とそれ以上はたぶん違う
私の場合特定のタイミングで急にグッと向上しました。初心者の場合繰り返し練習よりもこういう気づきで一気に上がるというのはあるのだなと自分の経験を通して感じました。
本当はプロに指摘してもらえば一番はやくて確実なのだと思います。ボウリングは再現性を高めるゲームなので、フォームの確立と固定が大事だからです。ただ私の場合ちゃんと習うというほどの熱意はなかったのと、そういう取り組み方は楽しくないので自己流でしたが。
一つ思うのは、何事も「習う」という姿勢を最初から決めこんでしまうと「試す」ということをおろそかにしがちです。自分の他の物事への取り組みを振り返るとそう感じます。
なおこの先、つまりアベレージ170から先はこうはいかない予感はあります。現状ハウスボールのストレートはアベレージ185くらいが限界と推測しています。
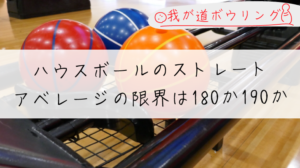
何事も限界値に近づくほど成長曲線は鈍ります。ここから先は気づきで劇的に上がるといったことはなさそうです。まさに繰り返し練習や微調整によってちまちまと上昇や下降を繰り返しながら、アベレージを1~2ずつあげていくしかなさそうです。
ただ140台⇒170までは「気づき」で一気にいけたので、実験や気づきって大切だな…という話でした。
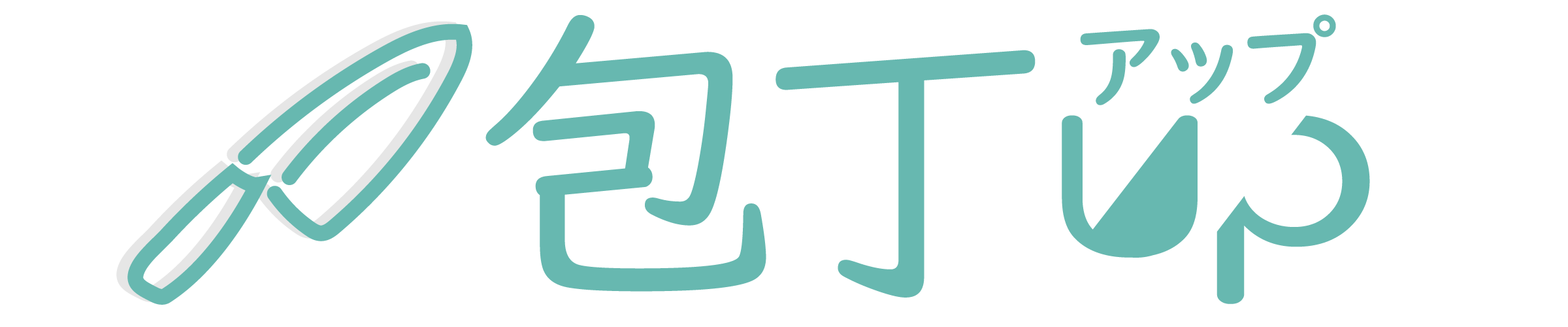
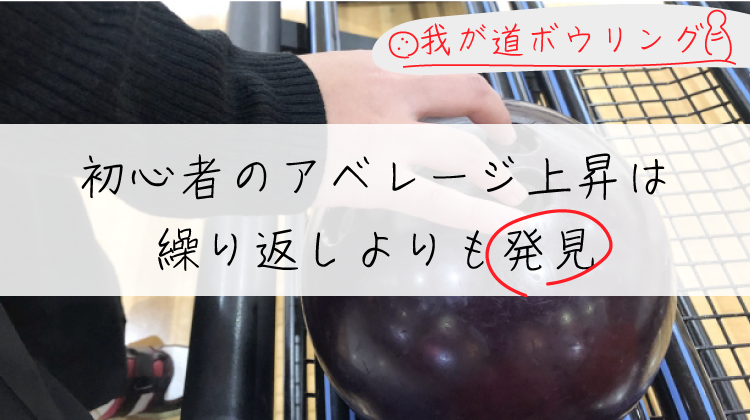
コメント