学校給食調理員はあまり技術を持っていない?いえいえ必ずしもそんなことありません。
というわけで「給食調理員」と聞いたら「こんなすごい奴だ」と思って間違いない6選です。素早く調理するためのコツも織り交ぜて紹介しています。
こんな人を見たら給食調理員です。
1.タマゴを高速かつ一定のペースで割り続ける
給食調理員の卵割りスピードを舐めない方がいいです。安定した速度で誰しもはやい。包丁のスピードは個人差が出やすいですが卵割りは大抵誰でもかなり速くなります。
何しろ一度に数百個を連続して割り続けるなんていうことは一般の飲食店員には絶対できない練習です。ド新人だとしても3回くらい担当(つまり卵2000個以上とか)すれば「有名オムレツ店のシェフやってました」と言いながら卵を割れば誰しもだまされるくらいの手際になるかも。
一個一個割りながら痛んでいないか確認しています。右手で卵、左手で小さなボール。左手で持ったそのボールに割り入れて確認。0.5秒で判断して流し入れつつ、もう右手は次の卵を割りかけているみたいな感じです。この確認は給食以外の調理現場でもやりますが、給食の場合一個でもミスすると数百個分の卵がパーになるかもしれないので確認は超重要です。
だたし実はカラが混入しまくっていることがあります。というより混入し放題だったり。でもOK。
なぜOKかというと、給食の場合卵はあらかじめ大きなバケツのようなものに割り入れておきます。そして卵のカラというのは沈むので最後の5㎜くらいを残して流し込めば大丈夫なのです。そしてその残した5㎜分も最後にゆっ~くり流せばバケツの底やわきにカラがひっつくため混入しません。
なお現場によるかもしれませんが、混ぜてから冷蔵庫保管すると細菌増殖の恐れがあるので割るだけ割っておき、使う直前に混ぜるというパターンもあります。その場合もカラはわりとすぐに沈むので入っていても問題ないです。給食で卵を混ぜずに使うことはほぼありません。
私はカラが入っても速ければOKという感覚がついてしまったので、普通の厨房に戻ってから困ることがたびたびありました。
2.玉ねぎの皮むきが速い
玉ねぎの皮むきスピードは給食調理員が誇れる技の一つです。冗談ではなくペティナイフと玉ねぎを持たせたら一流シェフに匹敵するスピードを見せる可能性すらあります。
玉ねぎは献立で登場する頻度が高いです。まとめて数十個以上は剥くことになるためどんどん上達します。
ぬるま湯に漬けてから剥くのが定番です。パリパリしないのでクルっと一発で剝けます。ちなみに飲食店ではぬるま湯に漬ける技は使いません。暇なときに剝いておいてすぐ使うわけではないからです。
ただし給食センターでは手で剥かないことがあります。主に機械を使うからです。機械の仕組みは芯を下にしてセットして蓋をすると、ドリルで芯がくりぬかれ、頭がちょん切られて、空気圧でシュッという効果音とともに皮が飛ばされる、みたいなやつです。

3.ピーラーが速い
給食調理員は基本的にピーラー(皮むき)が速いです。
なにしろ毎日早朝から野菜をひたすら剝きます。半分寝ながらでも使える感じです。おそらくピーラーを使わせたら和洋あらゆる職人も含めて最も速い気がします(職人だったらふだんから包丁で剝きますし)。
ちなみに私は学校給食の後、産業給食5000食などをやっていたので毎日10キロ箱何箱もの人参を剥き続けました。その結果ピーラーの横を持つのではなく持ち手の末端をちょこんとつまんで使うという技(腕をほぼ動かさないので疲れない)を発明しました。スピード&スタミナの両方で〇。ちなみにそこには定期的に調理専門学校の教育実習生たちが来ていましたが、皆が感動してくれたのは私の段取りや包丁さばきではなくピーラーのスピードでした…。
ちなみに給食センターだと人参の皮むき機もあったりします。でも給食センターの皮むき器は性能が悪く、結局手で剥きなおしたりしていました。
調理員はピーラーは得意ですが、包丁修行はしないので包丁での皮むきは苦手な確率が高いです。
4.人参のカットは得意
給食の人参使用率は高いです。ない日がないくらいですね。
なので給食調理員は人参のカットは得意です。せん切り、いちょう切り、乱切り、角切り、さいの目切り、なんでもこいです。ただしどれもよく見ると雑だから絶対によく見てはいけません。厚さとかあまりそろってないことも。
ほんとうに他の専門料理人が見たら怒り出すくらい雑だったり(あくまでそういう専門プロ目線でみたらダメなだけで、家庭レベルでみたら十分揃ってるんですが)。
あと給食で言う「せん切り」や「さいの目切り」は和食の料理人からみたらそうは呼ばないような別物です。でもサラダ用の「せん切り」だとしても85度以上に加熱するんだから仕方ないです。
給食系ではなんでも加熱するので普通の厨房に戻ったとき生食用の極細や極薄に切るのが苦手になったことに気づきました。
なお最新の給食センターだと角切り機などあらゆる機械が揃っていたりします。手で切るのは本当にこんにゃくと豆腐とブロッコリーくらいだったりします。
5.ジャガイモの芽とりも得意
ジャガイモの芽とりはかなり頻度が高い下処理です。
ちなみにじゃがいもの皮むき自体は機械でやります。自校式でも機械があります。機械のしくみは鉄ヤスリ的なものが底でグルグル回転しているようなところに上から投入、数分したらゴロゴロと横の出口から取り出します。やりすぎると小っちゃくなってしまうので注意です。機械のないところはきっとピーラーで剥いているのかなと思いますが、ない現場には出会ったことありません。
ちなみに芽とりは包丁や100均ピーラーのわきにある丸い部分とかではなく、芽取り専用のスプーン型のやつ(いもくり)を使います。なお芽とりはセンターでも手でやります。機械が苦手な仕事の一つです。
6.実は船頭になれる
…と思っています(私だけ?)
給食は回転釜という大きな鍋で作りますが、実はスープを混ぜるときのヘラ(スパテラと言います)の動かし方は、船頭さんが船をこぐ時の動きにそっくりです。ちなみにシチューやカレーなど水よりよほど重たいものを混ぜているので、嵐でも対応できるくらいの腕力とバランス感覚は自然に身についていそう。
不安定な船の上でできるわけなさそうですが、真夏に熱中症寸前で前後不覚になりながらかき混ぜ続けた経験を持たぬ調理員はいません。
ひたすら混ぜ続けないと焦げる、その結果何百人もの児童が飢えに苦しむかもしれない、そのプレッシャーで根性も相当鍛えられています。
…まあでも実際船漕ぐのは無理ですよね。船頭さん失礼しました。
個人的には逆パターンで船頭さんに回転釜混ぜてみてほしい願望があります。初めての人はまず回転釜をスムーズに混ぜられないものですが、船頭さんならいきなりベテランチーフ並みのスパテラさばきを見せてくれるかもしれないという期待が止まりません。
まとめ
大量調理をやっていると、繊細さは犠牲になりますがスピードとパワーと文明の利器を使うことにかけては随一になれます。以上給食調理員になると身に着く技術6選でした。


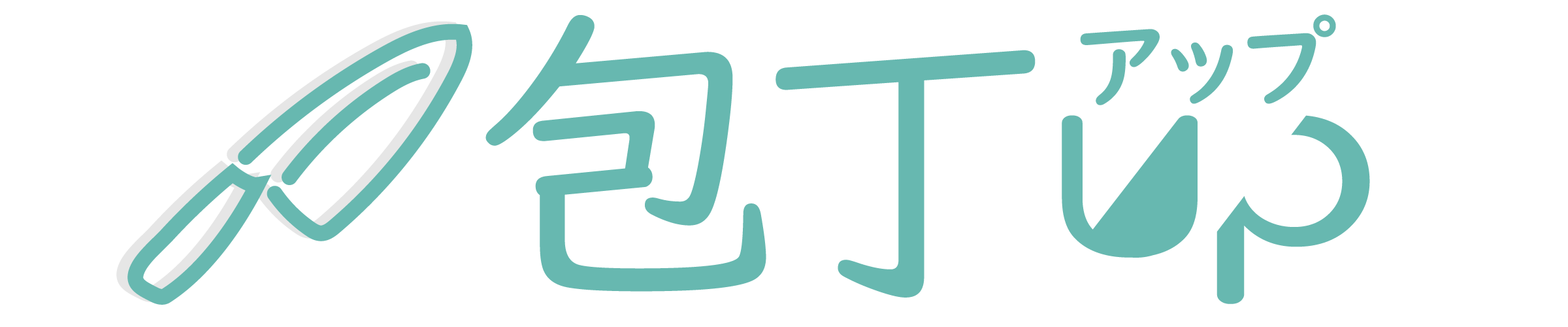


コメント