調理師試験の勉強。独学を考えている多くの方は、できるだけ時間とお金をかけたくないでしょう。この記事ではほとんどお金をかけずに、最速で合格ラインに達する方法をまとめました。
この記事の言葉の意味。
- 最安 →教材は1,000円以下(¥0でもOK)
- 最速 →丸一日分くらい(10時間以内)
- 確実 →100回受けて99回受かる
私は調理師資格持ちで元資格マニア(約35個)です。この記事に書いた方法で中小企業診断士などの難関資格、他にも宅地建物取引士など多くの国家試験に合格してきました。危険物取扱者(乙4)は知識ゼロからテキストなし0円、3日程度(数時間)の勉強で合格しました。最安、最速です。
なおこの記事は最初下記記事の一部だったのですが、長くなりすぎたので本体から分離したものになります。

記事の内容は調理師試験対策というより受験テクニック的な部分が強いです。調理師は勉強法さえ間違えなければ本当にお金をかけずに、ごく短時間で合格できるはずです。いろいろな資格試験で自分も実践し成功してきた方法ですが、東大合格者や難関受験成功者たちの考え方が元になっているのでぜひ参考にしてください。
調理師は覚える系の試験なので勉強の得意・不得意や頭の良し悪しは関係ありません。私も高卒ですしぜんぜん頭よくありません。勉強の方法を知っているかどうか、だけです。
よくある間違い
最初に資格試験の勉強法でよくある間違い(非効率な方法)
- ”まずは”テキストを買う
- テキストを「読む」
- ノートにまとめる
- 問題集を「解こう」とする
- 「テキストで学ぶ→問題を解く」の順番
これらは全部小中学校の典型的な勉強法ですが、こと資格試験の突破に関しては無駄だらけです。調理師試験でこれをやるとおそらく何十時間もかかります。
ただ私も最初はこういうワナにはまってずいぶん時間を無駄にしたこともありました。ただ資格が趣味になっていくにつれて、いろいろな受験テクニック情報に触れたり自分で試してきました。そして最速で合格点に達する方法を体得しました。
これからご紹介する方法なら多くの人が一桁の時間でいけるでしょう。では具体的にどういう手順が効率的なのかみていきます。
勉強計画全貌
→まず勉強に必要なものです。上から大切なもの順です。
- 調理師試験過去問アプリ(無料)
- 公式サイトの過去問(もちろん無料)
- テキスト(中古で数年前とかでよい、最悪無くてもいける)
ポイントはテキストより過去問の方がはるかに重要なアイテムという点(無料でよい)。テキストは最悪なくてもいいです。
→では勉強計画です。どんな資格試験でも概要はだいたい同じですが調理師試験の場合はこうします。
- まず公式サイトの過去問を何年度のものでもいいので1回やってみる
- 答え合わせをしながら、自分の実力と合格ラインまでの乖離(かいり)を知る
- テキストを一冊だけ選ぶ
- テキストの目次を見て全体像を把握する
- 最初から丁寧に読んだりせず、パラパラ1ページ30秒くらいで流し読み(やらなくてもよい)
- 【重要】無料アプリを使ってひたすら過去問をやりまくる(解説は斜め読み)
- 結構できてきたなと思ったらテキストに戻って適当に目を通す
- 過去問を本番形式で2年分ほどやってみて70点以上取れていればOK。だめなら6.へ戻る
まず注意点は4.~5.で、テキストをいきなり丁寧に読んだりしないという点です。いきなりちゃんと読むのはつらいですし頭に入ってきません。小中学校での勉強方式は挫折の原因です。
理数のように基礎→応用みたいな内容ではないので、5.のパラパラ読み工程すら飛ばしてもいいくらいです。まずは過去問アプリをやってから、その該当ページをパラパラでもよし。
いずれにせよ勉強時間の8割以上は6.の”ひたすら過去問”のみ。わからなかったら考えずにすぐに答えを見ます。むしろ最初は解こうとせずに答えだけ見ていく感じの方がいいです。
しつこいですがくれぐれもテキストを読んではいけません。勉強したつもりになるだけで超非効率です。ある意味すべての点で「ちゃんとやらない」が最速のカギです。
ではもう少し各部分を解説します。まずは1.の過去問からやるべしという話。
最初に教材を買わずに”過去問1回分”の理由
だいたいの人は勉強というと最初に教材選びをしてしまいます。ですがこれはおすすめできません。これはゴールを知らずになんとなくふらふらと歩き出して、その辺の店でアイテムをふわっと買ってしまうようなものです。
まず敵の強さとゴールを知りましょう。そして自分の位置(点数)を知ります。あとはその距離を埋めるだけ、という状態を作ります。
具体的にはこんな効果があります。
- だいたいどのくらいのインプットをすればよさそうか漠然とでも見えてくる
- 問題の傾向、レベル感がわかる
- 上記をテキスト選びに生かせる
- 最初から本番イメージができる→モチベーションアップ
- テキスト初見での把握力が上がる
これらによって点数に結びつかないすべての無駄を排除できます。時間も30~40分くらいあれば十分です。このわずかな時間と手間を最初にかけるだけでグッと効率的になります。
ちなみに危険物取扱者という資格に合格した時はこの最初の過程でテキストはいらないかも…となりました。結局ネット上の過去問を3回回していたら合格レベルに達してしまったので、テキストなしで受かってしまいました。
わからない用語だげググったり、まとめサイトを見たり、YouTubeの講義を見たり、それで十分という場合もあります。
本当に教材が必要なのかどうか、実はテキストは一冊も必要ないのではないか、という確認の意味でもこの過程(一番最初に試験問題をやってみる)を踏んだ方がいいです。
テキストを買う前にまず過去問、これをやったことがないという人は効果大なのでぜひ試してください。最初の実力を把握しておいて右肩上がりに点数が上がっていくのをゲーム感覚で楽しむのもおすすめです。
ではテキスト選びです。※テキスト1冊すら買わず完全に0円でも十分合格ラインにいける(過去問アプリを回していれば必ず届きます、ウソだと思ったら試してみてください)はずですが、一応テキストありバージョンで書きます。
テキストの選び方~過去問付きはいらない
テキストの選び方ですが、調理師試験の場合どれでもほぼ差はないので好みでOKです。
書店やAmazonからしっかり選びたいという場合、ポイントは2つです。
- なるべく薄くて簡潔なもの(イラスト・図などが多く、文字が少なくて見やすい)
- 過去問ページが多いものは選ばない(巻末にちょっとついているくらいなら許す)
なぜこの選び方がいいのでしょうか。
まず資格試験で重要なのは過去問です。暗記系のほとんどの試験は過去問と解説だけで受かります。テキストの役割は、全体像の把握と頭の整理のためです。知識をしまう場所をたまに整理する、それだけです。間違っても1ページ目から丁寧に読む必要はないので、パッと見てわかるやつがいいです。
そして過去問が大事なのに過去問がないやつを選ぶ理由は、過去問は無料で山のように手に入るからです。調理師試験の公式サイトと無料アプリがおすすめです。他にも過去問はネット上にたくさんあります。無料で手に入るのでそこにページを割いているテキストにお金をかけないようにしましょう。
ちなみに丁寧な過去問解説を読まないと理解できないような法律・ITの試験とかだったら過去問題集はむしろテキストより重要なこともあります。ですが幸い調理師試験は覚えるだけなので、解説がない過去問サイトとかでもOKなわけです。
”テキストは詳しいものが良い”は間違い
なおAmazonなどのレビューを見ていると
テキストにない問題が出た→テキストがカバーできていない→これ一冊では網羅できない
というような評を見かけますが、まったくの見当違いです。テキストですべて網羅する必要はありませんし不可能です。もし網羅しているテキストがあったら情報量が多すぎておそらく使いものになりません。また資格試験というのは毎年の合格率や合格点を安定させるために新出を必ず含めてくるものです(過去に出した問題を繰り返すだけだと年々簡単になってしまう)。
資格試験は6割取れればOKです。不必要に点数を伸ばそうとするのではなく、確実に6割を超えることが大事です(3回やって3回とも7割の方が、2回8割で1回5割よりも良い)。そして試験問題は基本的知識があれば確実に6割超えるように調整されています。難しい問題は混ぜられていますが、それはできなくてOKです。
ですのでテキストは細かいことが書いていないくらいのほうが使いやすいのです。実際に点数を伸ばす作業は過去問で行ない、たまに要点を整理するためにテキストを使います。

情報はいかに捨てるか、と言われますね。資格試験もよく出るところ以外はすべてばっさり捨てる、というのが正しいです。



量が多くて詳しいほど良い、はネットがなかった昭和の価値観なので捨てましょう。
ちなみにそのジャンルの知識ゼロという場合は、最初の一冊はマンガから入るのがおすすめです。勉強は最初の壁が一番きついので、イメージづくり・踏み台にします。でも調理師試験の場合は実務経験を積んでいるはずなのでこれが必要な人はいないでしょう。
「ひたすら過去問」について
多くの資格試験ではつまづきやすい箇所や点数が取りにくい科目というのがあります。でも調理師試験にはそういった部分はないので、ただ何も考えずに過去問アプリをやりまくるのみ。
過去問回しの際、最速を目指す上で重要なのは2点だけです。
- 考え込まないこと(一瞬で答えがわからない場合は間髪入れずに答えを読む)
- 解説はしっかり読まないこと
まず1.ですが、本番ならともかく練習の時点で当てようとするのはシンプルに時間の無駄です。
次に2.は時間対効果を考えたときに、解説を丁寧に読んで覚えようとするのはもったいないからです。その同じ時間に2~3問バッ~と眺めた方が多くの知識を得られます。
調理師試験は、解説をよく読まないと理解できない問題などありません。広く浅い知識を取り入れた方がいいタイプの試験です。また同じパターンのひっかけが多いのも特徴なので、解説を読むよりも単純に多くの問題に触れた方がお得です。
合格レベルの見極めについて
資格試験のワナに、”過去問で合格点を超える→なぜか本番でちょっと届かない”というものがあります。この理由は、たいていの資格試験では新出の問題が含まれるためです。
つまりテキストや講座というのは本物の過去問をもとに作られますが、みんながそれを使って勉強すると合格率が異常に高くなっていってしまう(相対評価の場合は合格点が高くなっていってしまう)ので調整しているわけです。
そのため過去問で合格点に達していても、本番では新出問題の分だけ点数が足りないという現象が起こります。なので過去問では一定の余裕を持って合格点を超えるくらいでないとだめなのです。
ただ調理師試験の場合はあまり気にしなくてよいとは思います。法律系資格における法改正やIT系資格における最新技術に相当するものがないからです。単に一定の割合でレアな知識を試す問題が混ぜられるくらいです。それは無視してよいレベルです。
とはいえたまたま知らない問題が多くて落ちたという不運を吸収できるくらいの準備はしないといけません。ではどのくらいできていればいいかというと最低何回やっても7割を超える完成度は必要でしょう(理想は8割)。このくらいやれば不運での変動を十分吸収できます。
ある程度過去問を回したら本番形式で2回連続8割越え、私なら最低ここまではやります。方法は公式サイトから本物の過去問を使うのがよいと思います。できれば印刷して時間をはかってやってみましょう。
過去問で合格レベルをはかる際は、+@の点数が取れていること。ぎりぎり合格レベルで安心しないこと。
合否判定基準の”あれ”について
調理師試験の合否判定基準は「全科目の合計得点が満点の6割以上」というシンプルなものです。でもあいまいなことが一つ書かれています。
「ただし、1科目でも得点が当該科目の平均点を著しく下回る場合は不合格とします。」
著しくとはどういうことか、本当に科目の平均点を元に算出するのか、いろいろつっこみたいですが、一般的に”0点の科目がないこと”と解釈されているようです。この真偽は不明ですが採点の効率などから考えると信頼できそうです。
いずれにせよ全科目まんべんなくやりましょう。「食品学は割と好き。栄養学は覚えるのがつまらないから捨てる。でもその分食品学で稼げるから大丈夫」。こういう考え方は最悪です。得意を伸ばすより苦手を潰す、これが資格試験の鉄則です。もし足切りルールがなくても同じです。30点の苦手科目を60点に上げる方が80点の得意科目を90点に上げるよりも確実で時間効率がいいです。
一番苦手な科目も6割、全体で7〜8割というくらいを目標にします。
ダメ(非効率)な勉強法
この記事では最速で合格に達する勉強法を書いてきました。反対にダメ(非効率という意味)な方法も紹介しておきます。
一番なダメな方法
一番ダメなのはこの記事で紹介したのと逆の方法です。
- 比重はテキスト>過去問
- テキストをノートにまとめる
- それを見て丸ごと覚えようとする
- 最後まで問題をやらない
ダメな理由は、問題の傾向を把握せずに覚えようとしてしまっている、アウトプットが足りない(引き出しから出そうとしないので記憶に定着しない)からです。
いまいちな方法
またそこまでいかなくてもオーソドックスなやり方(まずテキストを読む→問題集をやる)もいまいちダメです。
これをやると「まずテキストを読む」というところがロスです。完全に無駄とは言いませんが過去問と解答を流し見ていくやり方に比べると時間のわりにほとんど頭に入りません。やった気になるだけの苦行となってしまいます。
学校の授業スタイルでやろうとすると大量の時間と精神力を無駄にしてしまうので気を付けましょう。
まとめ
最速、最安、確実に調理師試験を突破する方法について書いてきました。
まず先生の説明を受けてノートにまとめ、その後練習問題をやるというスタイルとは全く違うので違和感を持たれた方もいるかもしれません。
ただこれは私の自己流とかではなく、多くの高学歴者や受験巧者が唱えていることを調理師試験バージョンで落とし込んだだけのものです(受験テクニック系の本を開けば同じようなことが書かれています)。
調理師試験は”よーし勉強するぞ”と息を整えて挑む必要はありません。まずはゴロゴロしながら調理師試験過去問アプリをやってみてください。数日後には「あれっもう合格できそうだぞ」となっている可能性大です。
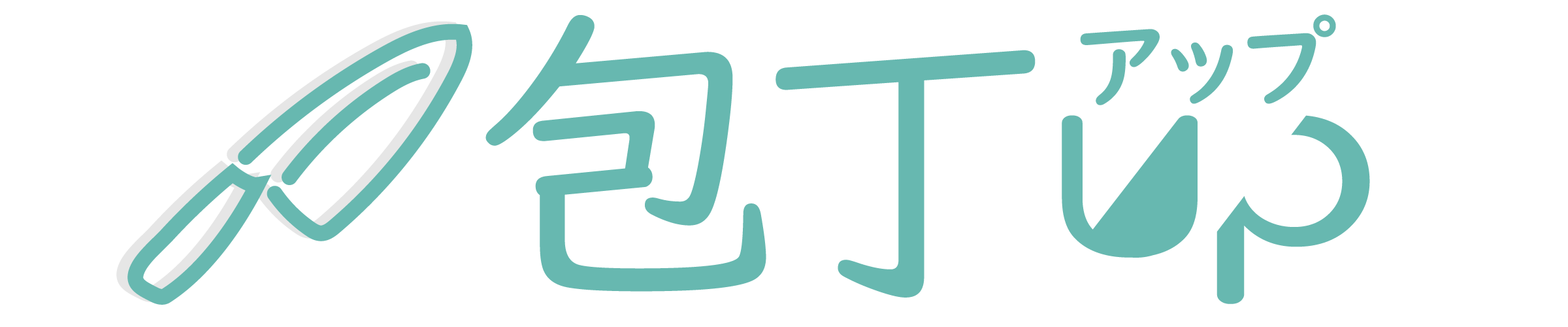
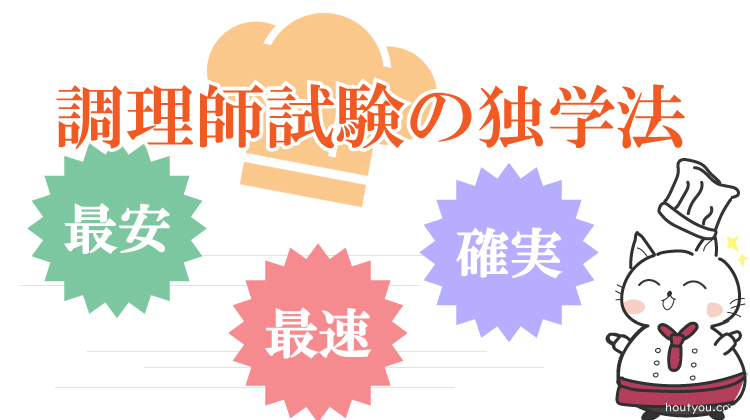
コメント