弁当形式の中学校給食がまずいと話題になったことがあります。
私も同じ方式のセンター(2つの自治体)で仕事をしていた経験があるので、中の人の視点で弁当方式給食(スクールランチ)の実態や問題点について書いてみようと思います。
弁当方式の目的とパターン

中学校では給食を「選択制」として実施することがありますね。



これはなんらかの事情で小学校給食のような「全員制」にしなかった自治体があるからです。
もともと家からの弁当持参が原則だったところ、給食を実施してほしいという保護者の声を汲んで導入を検討。この場合うちは給食はいらないなどの意見もあります。そこで折衷案的な感じで給食を選択することもできるようにした、などのパターンです。この場合当然食缶に入れた形でクラスに運ぶことは難しいので弁当形式の給食(スクールランチ)になります。
メリットの一つとして、個別に支払いを求めるので給食費滞納が起こらないというのがあります。
献立が2パターンある本当の理由
私がいたところは毎日AとBという2パターンを出していました。このパターンの自治体は多いです。生徒側としては好きな方のメニューを選べるというメリットがあります。
ただ実は作る側としても量が分割されるというメリットがあります。
給食ではスチームコンベクションオーブン(焼き物か蒸し物)とフライヤー(揚げ物)という機械を使います。メニューが1種類だとどちらかを使わない日というのが出てきます。
一方ABそれぞれのメニューで揚げ物、焼き物などを分散させる形をとることで、この2つの調理機器が毎日まんべんなく活用されるように献立を組むことができます。それにより大量のおかずを一定の時間に仕上げることができるようになります。冷却時間を取らなくてはいけない(つまりその分調理時間が圧迫される)弁当方式ではここは重要です。献立が増えるという手間をかけてでも機器をフル活用する必要があります。
弁当方式の問題点と実態
味と献立の問題点について
弁当給食の一番の問題点は暖かくない、ということです。テレビなどで一時期話題になっていた通り冷たいので評判は悪く残食が多い、という実態があります。実際に残食のあまりの多さに毎日悲しい気持ちになりました。ただしご飯だけは暖かい状態で機械を使って盛付、保温ケースにいれて配送するのでその限りではありません。
おかずは衛生上の規定によって10℃台までしっかりと冷やすので常温よりもさらに”冷たい!”です。
ただその温度そのもの以外でもまずいと言われる原因はおそらく3つあります。
- 汁物がないこと
- 薄めの味付けであること
- そもそも弁当に向かないおかず
1.汁物がないのは弁当給食なので当たり前ですが、もし配缶方式の給食でも汁物を無くしたら評判はかなり落ちるでしょう。配缶方式でもハンバーグなどはほんのり暖かい程度で熱々は無理です。そこを大きく底上げしているのが汁物です。
2.薄めの味付けについて。弁当給食はあくまで給食としては標準的な味付けになっています。つまり市販の弁当のような冷たくてもおいしいと感じる濃いめの味付けにはなっていません。つまり相対的に、弁当にしては薄味です。しかし給食という形でやっているので塩分をあまり増やすことはできません。また基本的にだしなども手づくりで取っているため、顆粒だしを多めに加えるなどの手段も取れません。※実際作り手として暖かい状態で味見すると普通の給食と比べて遜色ないのですが、完全に冷却した後はまずくなります。
3.弁当は本来固形のおかずの方が向いています。ただ給食センターの大量調理では機器・人員・時間の関係上どうしても炒め物などが多くなり、冷たい弁当に不向きなラインナップになります。
異物混入の可能性
弁当給食のメリットの一つとして異物混入(主に毛髪や繊維)を防げそう…というのは携わる前に思っていたことでした。理由は盛付作業時に発見できると思ったからです。
ですが実際にやってみると普通の配缶給食とトントンくらいでした。正確に件数を比較したわけではないので感覚ですが。
私なりに理由を考えてみると、工程が大幅に増えるからではないかと思っています。具体的には、できあがった料理を冷却用バットに移し替える→冷却後、盛り付け前に正確な計量をしながらバットに等分する→盛付の段階で数十人の作業者のラインを通る。これらの過程で混入のリスクが高くなっていたのではないかと思います。
喫食2時間前ルールのグレー
学校給食は喫食2時間前にならないと加熱調理はできない原則になっています。
調理後の食品は、調理終了後から2時間以内に喫食することが望ましい。
大量調理施設衛生管理マニュアル
でも弁当給食では冷却時間と盛付時間があるため9時には加熱調理を開始します。数ものの調理は食数が多い場合は8時頃から加熱しています。
では”2時間前ルール”はどうやって守っているかというと盛付開始は2時間前から、ということになっています。つまり12:30喫食なら10:30分盛付開始。盛付時間は約1時間。盛付時間中にも遠い学校を優先に順々にトラックは出発していくのでこれでギリギリのスケジュールです。
たしかに加熱調理後すぐに冷却をかけるので安全性にほとんど問題はありません。通常の給食が時間で安全を確保しているのに対し、温度で安全確保という考え方。なおもちろん配送も保冷車です。
ただあくまで加熱は喫食の2時間前というところにこだわればグレーな方式ということになります。でもマニュアルの文言をよく見ると「調理終了後から…望ましい」と書いてあります(つまりあくまで原則であり例外は認める)。あとは私もマニュアルを熟読してはいないので、なにか根拠があるのかもしれません。でも冷却すればOKだとすると何時間前から加熱作業してよいのか解釈が自由にできそうなのでなんとなく釈然としないです。



ここからは中の人目線で弁当給食の問題点をさらに深掘りしてみます。



労働環境が悪いといい給食が作れないというお話です。
調理員から見た大変さ→労働環境が悪いと味の低下に拍車
中の人だった視点から言うと弁当形式の調理員は通常の配缶方式よりも格段に大変です。毎日のスケジュール表です。
| AM5:30 | 出勤。各種チェックや準備。食材の検収。 |
| AM6:00 | 下処理開始。 |
| AM7:30 | 切り込みや成型作業。 |
| AM8:30 | 数もの加熱開始。 |
| AM9:00 | 釜調理開始。随時冷却。 |
| AM10:00 | 調理終了。随時計量・分割。 |
| AM10:30 | 盛付開始。全員参加のため掃除などもすべて中断。 |
| AM11:30 | 盛付終了。盛付場、調理場の掃除。 |
| AM12:30 | 休憩。 |
まず朝は早いですし加熱作業も8時台にはじまりますから午前に一息つくなんてもってのほかです。夏はせいぜい盛付開始前に水を一気飲みするくらいでした。一方通常の配缶方式の場合はAM7:00下処理開始、AM10:30頃以降にメインの調理スタートという感じです。
作業内容的にも冷却や計量作業の手間と体力的負担が大きいです。いったん大きなバット(番重)に移して冷却、その後総量を量りなおすというのが大変です。この作業で重いものをひたすら積んだり下ろしたりします。さらに計算して全バット(番重)同じ重さにならし、8区画に分割して1区画あたりの人数を割り出します。
盛り付けているそばからトラックに積み込んで出て行ってしまうのでミスは絶対に許されません。給食費で運営している以上多めに予備を取ることもできないのでギリギリです。一方普通の配缶方式なら万一多く入れすぎて足りなくなっても回収することができますし最悪ある程度適当でもOKです。
いったん盛付ラインが動いたら絶対止められません。出勤から昼までぶっ通しで7時間になります。
盛付作業を滞りなくすすめるために前日の準備や打ち合わせも余計にかかります。盛付の人員配置図も緻密にする必要があります。特に盛付の人員確保は大事です。ギリギリで運営していたので急な休みがでたりしたら盛付のためだけに応援を呼んだりします。パートも働きやすい環境ではありません。
まとめとして弁当給食は盛付と配送が重たい作業なので、イメージは下表のようになります。スケジュールや労力から考えると調理はあくまで下準備くらいの位置づけです。
| 方式 | 下準備 | メイン作業 |
| 配缶方式 | 下処理、数取りなどまで | 加熱、配缶 |
| 弁当方式 | 下処理~加熱、仮配缶、冷却 | 盛付、積込、配送、現地配膳 |
弁当方式には反対
なぜこういった現場の状況を書いたかというと、弁当方式はブラックな労働環境にもつながりやすいと思うからです。
社員の拘束時間は5:30~16:00でした。学校給食以外の事業(他の施設用給食・介護食など)も並行していたためにデフォルトで10時間以上、長い人は夜9時までとか15時間拘束くらいになっていました。
このような業務の並行は会社の方針に問題があるだけですが、まずそもそも昼休憩まで7時間ぶっ通しになるようなスケジュールは問題です。
実際離職率は限りなく高かったです。冗談ではなく「2年やったらベテラン」みたいな状態でした。これでは人も育たず現場も安定しません。”まずい給食”に拍車がかかる原因になりますし、最悪安全確保も難しくなるでしょう。
これで生徒からの評判がいいなら意義もやりがいもありますが、残食だらけの不評な給食なのでもはや意味を感じません。
なんらかの改善を
不評な弁当給食ですが、実際に助かっているという保護者の声も少なくありません。また必ずしもまずいまずいという自治体ばかりではありません。実際私のいた自治体も「冷たいからおいしくない」という声は多かったですが、問題になるほどまずいという評判ではありませんでした。
ですので単に廃止したほうがよいということではなく、例えば以下のような方策も検討できないだろうかということです。
生徒の満足度の向上
- 汁物だけは配缶方式でつける
- 暖かい状態で安全性を確保する
特に汁物をつけるのは企業向けの弁当では定番の人気サービスなので有力です。ただ学校の場合は注文していない生徒が食べようとする、昼食時間の問題などがあるので難しいところです。また提供側の負担もさらに増えます。暖かい状態での安全確保ができれば最高ですが、現実的には難しいです。
調理員の労働環境改善
- 弁当給食方式にするなら自治体が労働環境を整えられるだけの委託費用を出す(通常給食以上の予算が必要)
- 調理員の労働状態についても基準を設けて、クリアしたホワイトな業者のみを対象にする
まとめ
弁当方式(スクールランチ)は以下の点で問題が多いというお話でした。
- 弁当方式がまずい理由のメインは冷たいから。ただそれ以外に汁物がない、味付けやおかずの種類が弁当向きではない等もある。
- 給食の特性上現場の努力による改善は限界がある。
- 弁当方式は調理員の労働環境がブラックになりやすい。
経験者としてこの方式に対する問題を感じていたので記事にしてみました。
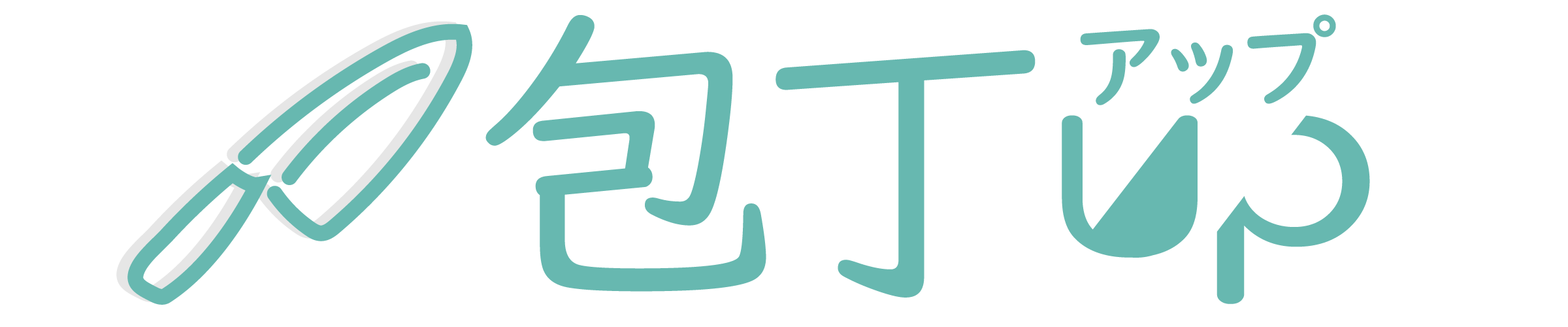
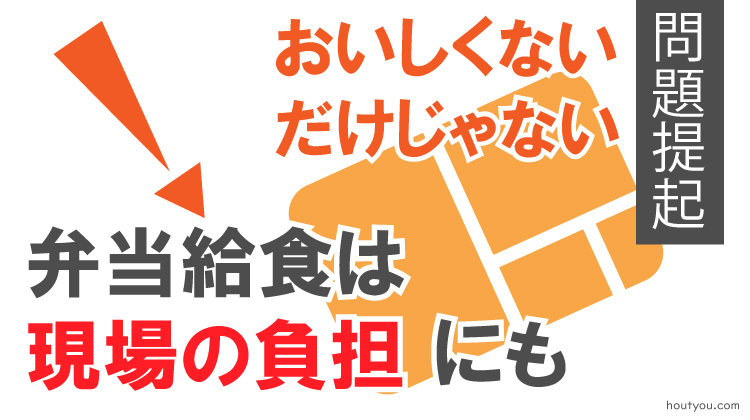
コメント