料理を仕事にしようとする時、また転職先を考える時に出てくる時に迷うことの一つは専門的な道(職人)を選ぶかどうかということです。また自分自身が職人を目指さなくても、店長候補やホールとして専門的な企業や店に入るかどうかという迷いが出ることもあります。
この記事では専門職(専門店)を選ぶことのメリット・デメリットについてまとめています。この記事の内容をしっかり考えてみることで後悔のない進路を決めることができるはずです。
まずは専門職にはどんなものがあるかみてみましょう。
料理の専門職(専門店)にはどんなものがある?
- 寿司職人
- 天ぷら職人
- うなぎ職人
- そば・うどん職人
- パン職人
- パティシエ
- ショコラティエ
- 和菓子職人
- ソムリエ
- バリスタ
これは一例ですがまだまだたくさんあります。もちろん日本料理やフランス料理も専門職ですが、この記事では上記のようにより深く一つのジャンルを追求するものに特にスポットを当てています。
料理の職人になるメリット3つ
将来安定した収入になる可能性が高い
専門的な道を選ぶことで職人として比較的安定した収入を得ることが可能です。
もちろん経営や営業に密に関わらない限り年収はある程度のところで止まります。ですが近年では余計なストレスを抱えたくないという理由でサラリーマンでも出世したくない人が多いくらいなので、プレーヤーとして安定した収入を得られるというのは魅力大です。

腕一本で食っていくかっこよさがある
職人はまさにその腕一本で一生食べていくことができます。世のサラリーマンも「手に職がある」ということに憧れる人が多いです。ある程度のポジションになると尊敬されますし、業界内に限らず一目置かれるようになります。
職人のコンテストなど腕を認めてもらう機会も多いです。ごく一握りですが国内外で知名度があがり、書籍出版やメディア出演する人もいます。
一生好きなことを追求できる
自分はこれが好きと言い切れるジャンルを選べたなら最高です。一生本当に好きなことをしながら人に喜ばれます。
料理人は料理が好きでなる人が多いですが、一つのジャンルを追及できる人は多くはありません。その専門的な視点や切り口をベースにしつつ、他の料理ジャンルから新しさを取り入れるなどやりがいは尽きません。
料理の職人になるデメリット3つ
門戸が狭い&修行期間が大変
本当に高い技術を求める人が一流店や一流の職人の元に集中するので、門戸が狭くなります。またそれでも人が集まるため一流店ほど入社後が厳しいという構図にもなります。
専門性が高いジャンルほど、またしっかり職人を育成している店ほど修行の期間が大変になります。専門店は大抵のチェーンよりもよほど駆け出し期間の給与は低く、月額~15万程度ところも多いです。中堅でも大手飲食店チェーンの店長などよりぜんぜん低いです。本当に好きでないと続けられません。
また給与以外でも労働時間の長さがあります。かたち上は交代制にしていても、実際新人は朝一番に出てきて一番遅く帰るというのが普通です。店や業種によりますが毎日15時間拘束などを覚悟しなければならないこともあります。
進路や転職の幅は狭い
特定のジャンルで修業して腕を磨く場合、転職する際にも同じ業界内から選ぶことが多くなります。他のジャンルに行っても経験が生きないからです。特に年齢を重ねてから改めて未経験のジャンルにいこうとしても、給与や人間関係の点から難しくなります。
将来管理職への道がある会社もありますが、多くは一生職人を続ける覚悟が必要になります。独立して自分の店を構える道ももちろんありますが、主に自分自身が職人として腕を振るうことになります。本当に好きなら最高ですが、そうでないのに選んでしまうと進路の選択肢の狭さに悩む可能性があります。
ただ専門技術を習得した人はその人間性や希少性自体を高く評価されることも多いです。飲食業界全体が人手不足ということもありますので、転職時の待遇にこだわらなければ途中から違うジャンルにいくことは十分可能です。また寿司職人などの場合は業界内でも進路が広いです。海外進出から格安チェーンまで様々な客層を相手にした多様な業態があります。大きなチェーンで管理職を目指すこともできますし、地域の限定的な社員として高収入で働くこともできます。
食糧事情など変化に弱い
特定の食材やルートに頼っている業界の場合はその影響をダイレクトに受けます。
特に輸入食材に頼っている業界では国際事情の影響で供給がストップする可能性は常にあります。また国内でも収穫量・漁獲量などが限られている食材では供給の影響をダイレクトに受けます。近年ではウナギが代表例ですが、今後環境問題や世界情勢の不安でいつ何が問題になるかは読めません。特定の食材を専門に扱う業界では「和食」など広い守備範囲の料理と違って他の食材に代替することができないので問題が起こったとき一気に厳しくなります。
さらには特定の食材や地域への風評被害の問題もあります。2020年も年明けすぐにCSF(豚コレラ)のニュースがありました。このようなヒトへの感染がないニュースでもダメージを受けることがあります。
まとめ
料理の専門職を選ぶメリット3つ
- 将来安定した高収入になる可能性が高い
- 腕一本で食っていくかっこよさがある
- 一生好きなことを追求できる
料理の専門職を選ぶデメリット3つ
- 門戸が狭い&修行期間が大変
- 進路や転職の幅は狭い
- 食糧事情など変化に弱い


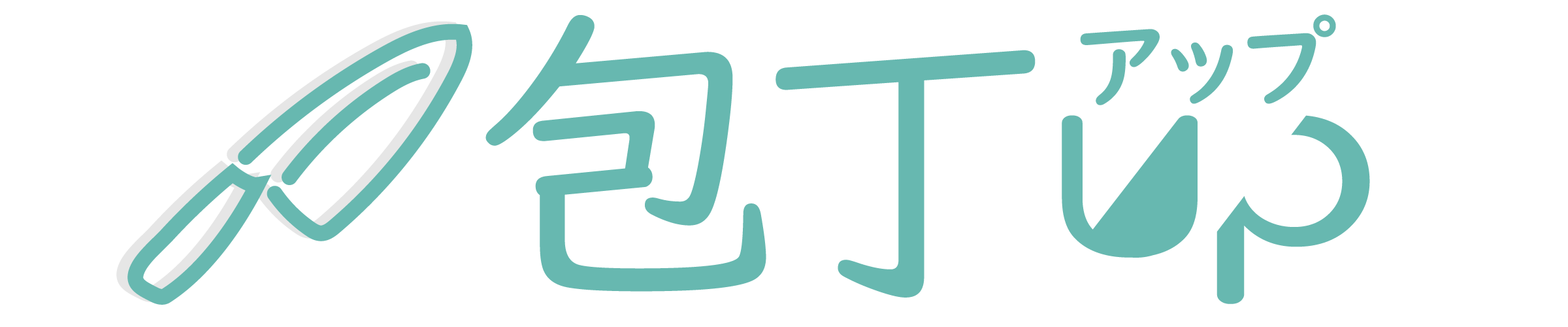
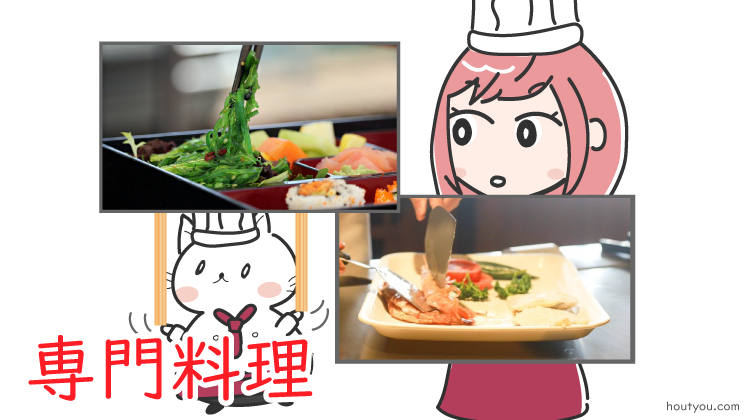
コメント