料理と盛付、色合いって奥が深いですよね。料理を真剣にやっている人ほど色彩の重要性を知って、きっと繊細に取り組んでいることと思います。
私は調理師歴約15年からWebデザイナーに転職しました。全く畑の違う業種ですが意外と共通していたのが「色」の重要性でした。
デザイナー歴は2年目とまだ短いですし、調理師としては給食などが長く専門料理をほとんどやっていないのであまり偉そうに言えないのですが、この記事では料理と色彩検定の関係についてまとめてみようと思います。
※色彩検定はWebデザイナーとしての勉強のために3級を取得し、現在2級のテキストを学習中です。
色彩検定で料理で役立ちそうな部分
色の組み合わせ方を学べる
色彩検定の大きなウエイトを占めるのが色の組み合わせ方です。
料理は色のコントロールに限りがあります。印刷物や工業品は自由度が高いですが、料理の場合食材の色は決まっているからです。そしてもちろん自然の色合いを生かす方が美味しそうに見えます。となると色の組みあわせがキモになります。
調理現場では「伝統的にこうしている」「これが決まったパターンだ」という考え方が強く、そこで思考が終わっていることも多いです。色の調和・構成などを論理的に学べば、なぜそれが美しいとされているのかを確認できます。それが応用力やオリジナリティの土台になります。あるいは”お決まりのパターン”を根拠を持って打破していくきっかけにもなりえます。
また色の心理効果も学べます。一品目や最後の品でどういう印象を与えたいのかなど、色の観点からも演出を考えることができるようになるかもしれません。
彩度、明度という尺度が加わる
料理では献立や盛付の際に色相(赤や緑など色の種類のこと)という概念だけで考えがちです。でも実際には色は色相以外に明度・彩度という3つの要素で成り立っています。「色の三属性」と言います。
- 明度…色の明るさ
- 彩度…色の鮮やかさ
料理では自然に「薄口にする」「ざらざらしている」「とろみ(ツヤ)を出す」などの認識をしていますが、こういったことを三属性の観点で捉えるようになると面白いです。
「この質感(明るさ・鮮やかさ)の皿の場合、料理はこの系統が合うかもしれない」など、イメージが膨らむようになるかもしれません。
空間や照明なども工夫できる
色彩検定では、光や眼などの色彩を認識できる根本的な仕組みを学びます。照明は料理店の演出を考える上で重要な要素の一つですが、改めて学ぶ機会というのは少ないのではないでしょうか。
またインテリアという実践的な内容もあります。床、壁、小物などの組み合わせや空間ごとの心理効果などが学べます。
このように色そのものというよりも照明や空間という概念を学ぶ機会になるので、将来独立や店長・料理長を目指しているという人には役に立つと思います。
色名が学べる
色彩検定では「慣用色名」というものを学ぶことができます。JISで選定されている慣用色名は269色あり、3級ではこの中から一部が出題されます。
例えば、
- 赤系統では「桜色」「紅梅色」「サーモンピンク」「ワインレッド」
- 黄系統では「芥子色」「オリーブ」「山吹色」「レモンイエロー」
などが出題範囲の一部です。
上ではあえて食べ物や自然から取られた色名を挙げました。このように慣用色名は食に関係する名前がとても多いです。料理と色の結びつき、その重要性がよくわかります。
特に日本料理では「見た目」を重要視してきた経緯がありますので、色彩検定はその本質に直接関係してきます。色の和名なども学べるので、板前や和菓子職人として表現やコミュニケーション力も向上すると思います。
料理人が色彩検定を取る価値はある?
ここまで見てきたように色彩検定と料理は十分な関係があります。では料理人なら取る価値があるのかという話ですが…
まず、料理人が「色彩検定持っています」と言ったり、履歴書に書いても価値はほぼ0だと思います。つまり取得したからといって料理人としての実力の証明になるということはありません。なぜなら試験で試されるのは、基礎となる知識や考え方があるかだけなので。それを仕事で応用できるかはまた別です。(1級などは「どう活用するか」という点も試験内容です。ただやはり実際の料理で活かせるかは別問題です。)
ですが資格としての価値・ステータスはなくても、学ぶ内容が役に立つ可能性はこの記事で書いた通り十分あります。
色彩の基礎を日々意識しながら仕事をしたり生活を送ったりすればまちがいなく差がついていくと思います。土台がなければ何も積みあがりませんが、資格を取得することで否が応でも意識しますし考察できるようになります。例えば何気なく広告を見ていても色がこうやって組み合わされているから見やすいのか、など発見が多くなります。当然料理に対する色の感度も高くなるでしょう。
最初はゼロとイチの差かもしれませんが、年月が経つにつれ大きな差になっていく可能性は十分あります。取得がゴールではなく、取得してからどのように知識を活用していくかが重要な資格です。
※ちなみに色に関する資格としては「カラーコーディネーター」もあります。こちらも基礎部分は同じような内容なので料理に役立てることができると思います。ただ同じ3級で比較すると色彩検定は合格率約70%に対してカラーコーディネーターは約60%となっています。カラーコーディネーターの方が覚えることが多くやや難しいとされているので、初心者は色彩検定3級からはじめるのがおすすめです。
色彩の重要性は増してきている
この記事で書いてきたように、料理人の実力の証明という意味では資格は不要です。ですが学ぶことにはたいへん意味があります。
WebやSNSで発信するのが当たり前になった現代は見た目の重要性がかつてないほど増してきています。特に料理はそうです。昔は料理人=頑固で寡黙な職人という色が強かったかもしれませんが、もうそんな時代でもありません。飲食店の営業力も料理人の発信力や工夫にかかっています。
色彩の知識というのは一度学べば無駄にはならないでしょう。料理そのものを現場で学びつつ、それ以外の学びもしたい、そんな人には色彩検定はおすすめです。
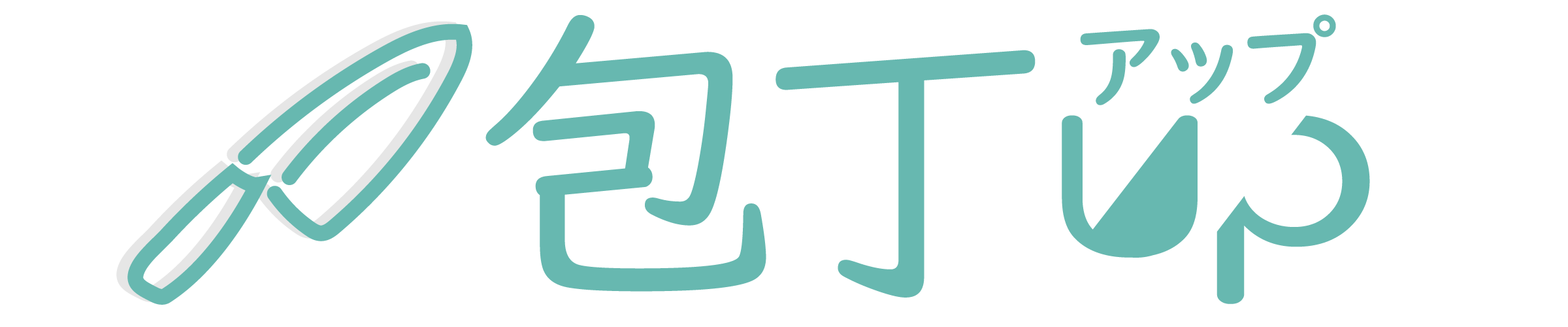


コメント