切れない包丁を使っていると多くのデメリットがあります。この記事では切れない包丁を使い続ける危険についてまとめました。
切れない包丁のデメリット
切れない包丁を使わない方がいい理由として
- 余計な力が入るので万一手を切った時に大けがになりやすい。
- 食材の細胞がつぶれて旨味が流出する、切り口の見た目も悪くなる。
などはよく言われることです。
これらのデメリットももちろん大きいですが、ここでは別のもっと長期的なデメリットを取り上げたいと思います。
力を入れるのが当たり前になってしまう
スポーツなどでもリラックスすることが大事だったりします。
初心者や包丁が苦手な人を見ていると肩をいからせていたり、包丁を必要以上に強く握りしめていたりすることも少なくありません。姿勢も極端な場合まな板をのぞきこむような前傾姿勢になっていることもあります。
慣れないから体に力が入ってしまうというのは仕方がない部分もありますが、包丁が切れないと余計にそれがエスカレートします。こうなると慣れてきてもこの状態からからだが抜け出せないという危険があります。
「包丁を使う=力を使う」という体の間違った思い込み。これでは慣れてきているのに包丁を柔軟にコントロールできないという期間が長くなるかもしれません。力で切っている感じの人はある程度スピードはあってもコントロールでは劣ります。逆に完全に余計な力が抜けている人はスピードはもちろん、とにかくコントロールがいい、包丁が伝えようとしている力に無駄がないので動きも常に安定している感じです。
切れない包丁を使っている=余計な力が入る。切れる包丁を使っている=リラックスするできる。
「切れる包丁だと怖い」にならない意識
包丁は道具なので、できるだけ道具のポテンシャルを引き出す使い方をしたいものです。ポテンシャルを引き出すとは、包丁の切れ味そのものに切らせ、右手は最低限の力だけを補うイメージです。刃が軽く入っていくなら力を抜き、入っていかないならその分だけ力を足していく感じと言えばいいでしょうか。
これが逆だと上達はおぼつきません。つまり、右手の力は常に入っていて包丁はその力の出口というイメージではダメということです。これだといわゆる「切れる包丁だと怖い」という感覚になってしまいます。
包丁は手の延長線上にあります。ただ力のイメージとしては、まず包丁があってその土台として持っている手がある。ですので包丁を落とさないようにつまんでいるくらい軽い感覚で使うことも多いです。
さらに切れ味以外にも重さで切ったり、包丁の形状を生かして切れるようになると、道具のポテンシャルを引き出していると言えます。
力が入ると姿勢が悪くなる、疲れる
あとは余計な力が入っているデメリットとして、腱鞘炎になりやすい、肩がこるという問題もあります。
肩こりについては、包丁使用時肩が普段より上がっているなら少し力が入ってしまっていると思います。そんな時はいったん肩を回したりして肩の位置をリラックスしている時の位置に落としてみるのがいいかもしれません。
また、リラックスできている人は基本的に前傾姿勢にはならないので(背が高い人は仕方ないですが)腰痛などの原因になることもありません。
何事もリラックスしている時が一番楽しいですし、包丁を持つのは毎日のことですから、切れる包丁で余計な力をぜんぶ抜く習慣は大事です。
切れる包丁を使って上達を早めよう
切れる包丁を使うと上達が早くなる理由を再確認しましょう。
1.素材の味を生かせる
切れない包丁では刺身やトマトなど柔らかいものは崩れてしまいます。細胞がつぶれて旨味が流出、舌触りも悪い、等々味に悪影響を及ぼします。
2.素材についてわかる
いつも切れない包丁を使っていると何を切っても抵抗があるので材料の質感・状態がわかりません。例えば、同じかぼちゃでも一玉ごとに違うことがあります。
切れる包丁を使っている方がその違いを感じ取りやすいので、今日のかぼちゃは水分が多いようだから、早めに火からおろそう、味も少し調整してみようといった基準にもできます。魚を捌いていても脂ののりや鮮度を感じられるようになります。いわゆる「包丁を入れただけでわかる」。
このように材料の質感を感じ取れるようになると料理上級者への道が開けてきます。
日本料理のベテランの場合、切れすぎる包丁に仕上げると逆に材料の感じがわからないので、少し切れ味をとどめておくということもあるそうです。
ここまでになる必要は普通ないと思いますが、材料によって切れていく感じが変わることがわかると楽しいですし、なんとなくでも素材や料理に必要なカンは磨かれていくものだと思います。
3.コントロールに集中できる
切れる包丁を使うとリラックスできます。何事もリラックスするほうがコントロールがよくなります。手(腕)の意識としては、「力で切ろう」ではなく「コントロールしよう」となります。これが本来の手の役割です。
やがて正しい使い方さえしていればまず手を切るなんてことはないという自信がついてきて好循環になります。
一方切れない包丁を使っていると、切れる包丁を持った時その余った力があだとなって指を切ってしまう、結果「怖い」という悪循環になります。本来は「切れない包丁の方が怖い」はずですが、それは切れない分余分な力をいれるからコントロールが難しくなるということです。
4.重さで切るという感覚、重心を意識できる
100均の包丁を使ったことがある人なら、持ってみてまず感じたのは軽いということではないでしょうか。100均の包丁も研ぎさえマメにしっかりしていればそれなりに使えますが、いかんせん重さだけはどうにもなりません。軽すぎる包丁を使っていると重さの力を利用できない、包丁に重心があるという感覚がわからないということになります。
使い方によってはそれで問題はないのですが、材料を「叩く」ような使い方をする場合に影響がでてきます。例えばきゅうりの小口切りは、日本料理では「打つ」という言い方をすることがあります。これは切るというよりトントンと上から包丁を落とすように切れというイメージからきています。
切れる包丁にしておけば重さを最大限活用することができます。
5.料理をしたくなる、包丁が手に馴染む
使い心地がいいものほど触る回数が増えるので当然上達が速くなります。また道具に愛情を持てれば、これをもっとうまく使えるようになりたいと思います。
そういう意味では道具から入る、カタチから入るというのも悪くないのかもしれません。使い慣れた一本があると、料理人が口にする「手に馴染んだ包丁」という感覚に近づけます。
高価な包丁を選ぶ必要はない
切れる包丁というのは必ずしも高価な包丁という意味ではなく、メンテナンスが良い包丁という意味です。どんなに高価な包丁を買っても、研がなければやがて研いでいる安物よりも切れ味は下になります。
家庭用として個人的におすすめのランクは最低4,000円~5,000円台くらいです。中途半端にケチって2,000円~3,000円以下くらいを選ぶなら5,000円近くまで上げて検討するといいでしょう。
もう少し出せる10,000円くらいの予算が取れるという場合は、GLOBALやヘンケルス(ツヴィリング)、藤次郎プロなどがおすすめです。仕事用・家用ですべて使ったことがありますが、家庭用としては十分すぎるほどだと思います。
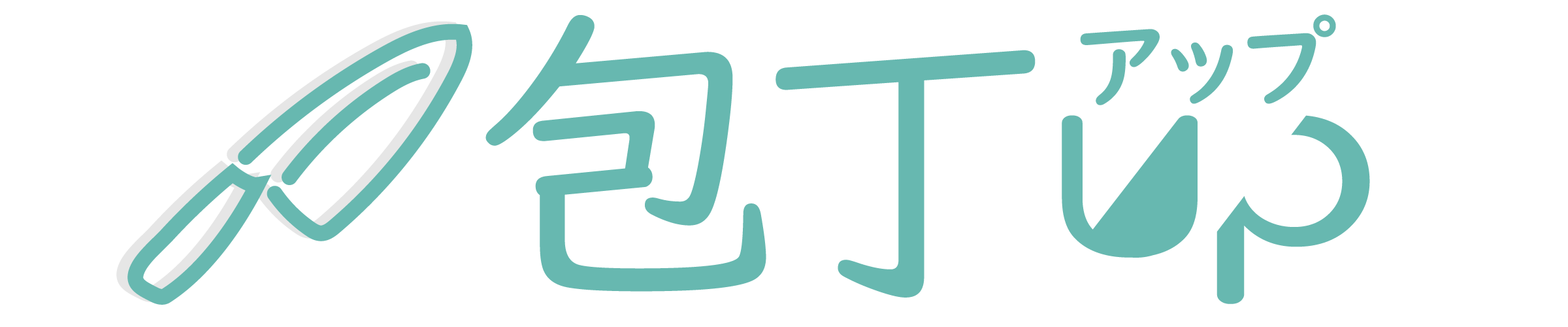
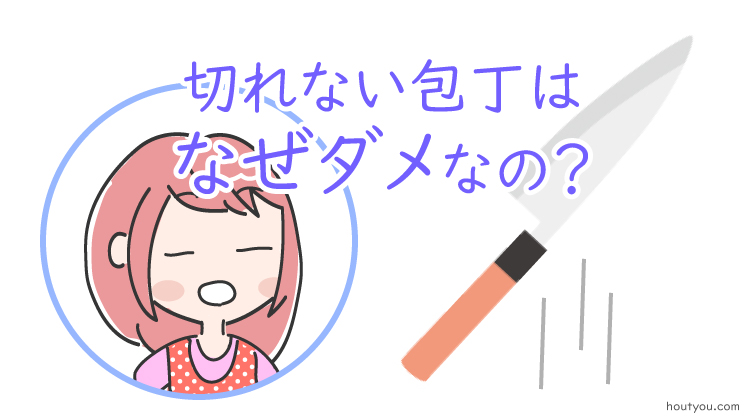
コメント